デンマークに学ぶ
『デンマークに学ぶ』 福祉、教育、エネルギー
前原遼さんの卒論(鹿児島大学橋爪ゼミ) | 橋爪太作さんのレポート(東京大学)
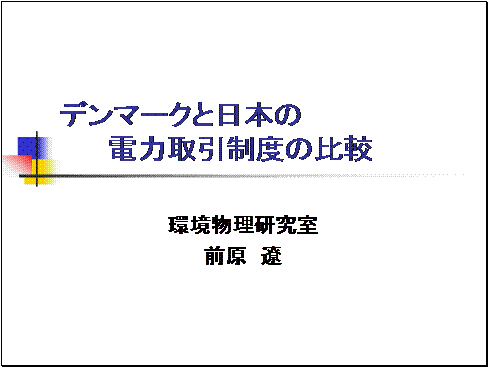
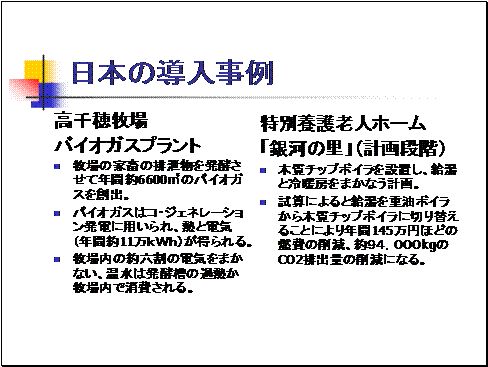
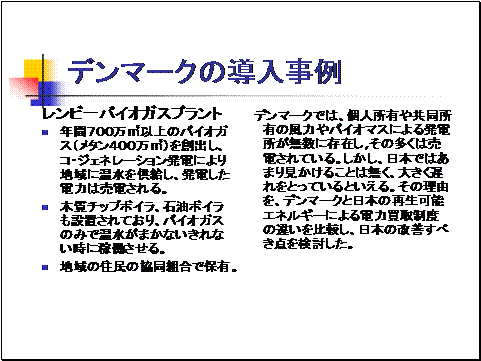
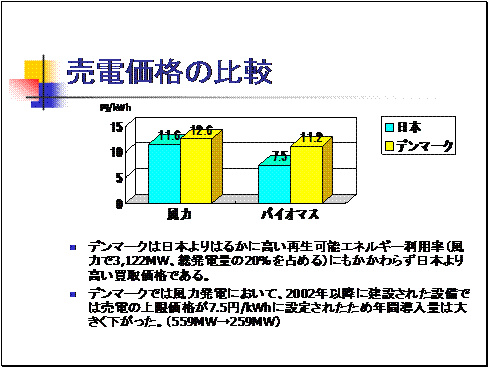
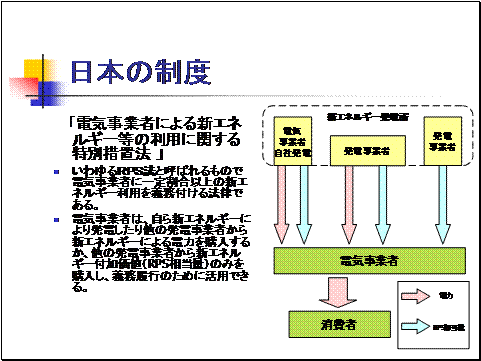
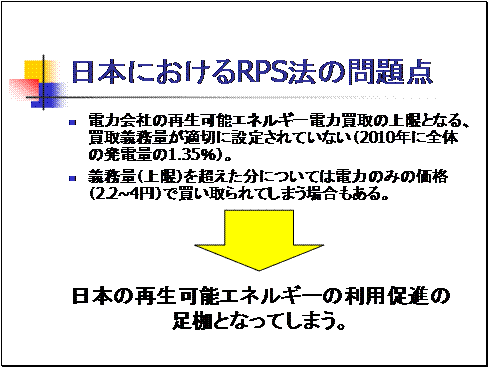
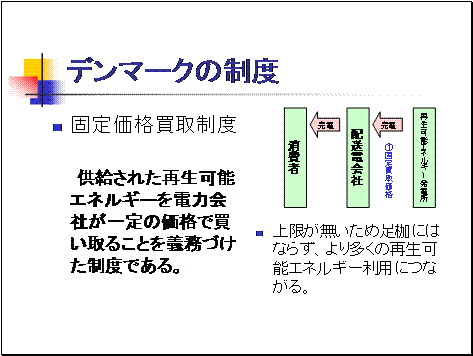
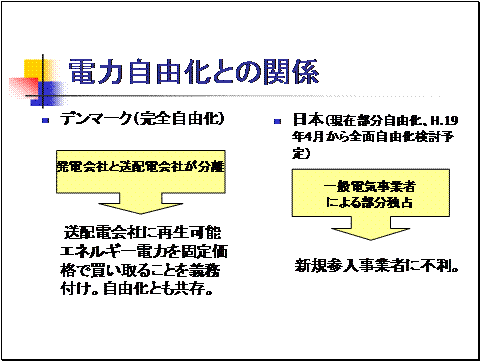
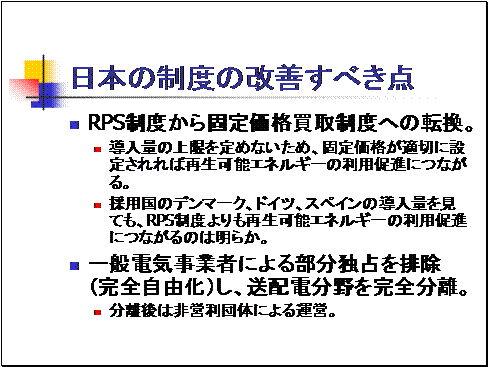
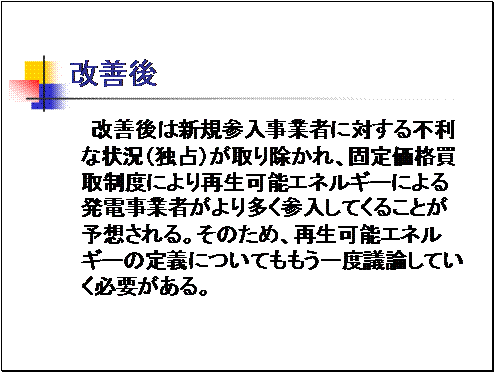
|
デンマークオルタナティヴ・エネルギー運動の史的展開
野生の思考としての“無縁”
橋爪太作 はじめに 網野善彦という歴史家は、私にとって非常に大きな存在である。18才の時に偶然手にした“異形の王権”という一冊の書物は、それまで私が前近代の日本社会に対して漠然と持っていたカビ臭い常識の数々を根本から激しく揺さぶり、そのうえ、見たこともないようなダイナミックで魅力的な中世の風景を次々と展開させていった。すっかり日本中世史に魅了されてしまった私は、図書館で網野善彦と名のつく本を片っ端から借りてまわり、余勢を駆って他の歴史家の書いた本も手当たり次第に(とはいっても80年代の社会史系の本が多かったが)読破した。その後、興味の対象が狭義の歴史学から社会学・人類学の方面に移っていった後も、その中心には常に網野善彦という存在があった。 今回、“無縁・公界・楽”をほぼ2年ぶりに再読した。読み進めていく中で、以前読んだ時には気付かなかったような様々な発見が数多くあったが、その中で、網野の見いだした“無縁”という概念は、単に日本中世史学の狭い枠にとどまるものではなく、危機に瀕しつつある巨大産業文明のオルタナティヴを歴史的・文化的な文脈から示唆するという、現在人文諸学全体に課せられた非常に重要で、かつ今日的な課題に対し、ひとつの根源的な解決方法を示唆することができるのではないかという思いが強く湧き上がってきた。 1960年代末の世界革命ムーヴメントが近代の終焉を宣告した後、それに代わる新たな社会モデルを創り出そうとする動きが、世界中のあちこちで生まれてきた。ありとあらゆる社会システム、ありとあらゆるオルタナティヴテクノロジー、ありとあらゆる思想が実験され、風力発電、地域通貨、分散型コンピュータネットワーク、エコロジー思想等々、ここから生まれたものは数知れない。そして今、これらは実験段階を抜け出して、近代西洋文明という沈みかかった泥舟を、未来への方舟へと作り変える困難な大事業にいよいよ取り掛かろうとしている。 これらの運動は一見すると、日本中世における自由都市や非農業民の存在形態に見いだされる無縁とは、何ら関連性が存在しないように見える。しかし、その実両者とも、人類史的普遍性においてまったく共通の根を持った存在なのである。それは、レヴィ・ストロースが野生の思考と呼んだような、石器時代いやそれよりもっとずっと遥かな昔、まだヒトが人間でなかった頃にさかのぼった起源を持つ、人類の精神構造に刻まれた平等/対称性への希求の現れであるといってもよい。この小文は、具体的には主に北欧デンマークにおけるオルタナティヴ・エネルギー運動の展開を題材にとって、現代/未来史における無縁のありようについて描写しようとするものである。
ところが、今や国の一大産業と化したデンマークの風車発電の歴史を辿ってゆくと、その始まりは、大企業や国といった利害得失に絡みとられた巨大組織ではなく、デンマークの各地に点在する小さな町工場や、ヒッピームーブメントの影響を受けた若者たちの無償の情熱にあるということがわかる。網野の言い方を借りれば、有縁の大組織ではなく、ちいさな無縁のネットワークの中から、新時代を創るあたらしい動きが生まれてきたのである。そもそもデンマーク近代発電風車の祖とされるポール・ラ・クール自身が、既に物理学者としてアカデミズムの世界で名を成したあと、19世紀後半にデンマークを席捲した農民運動に影響されて民衆教育の世界に身を投じた異色の人物であり、その思想的基盤には、いわば草の根からの文明開化ともいうべき、農民自身が管理できる規模でのテクノロジー開発があった。彼はアスコー・ホイスコーレにおいて、精力的に風車発電システムの開発と技術者の教育を行い、それまで都市のブルジョアのだけものであった電気を、農村にひろく普及させる運動を推進した。本当の意味での農村の近代化を目指し、地に足のついた技術を造り出そうとした点において、彼は日本の宮沢賢治などとも非常に思想的に近しい間柄にあるといえる。じっさい、賢治の国民高等学校はデンマークのフォルケホイスコーレの直訳なのである。(デンマークのホイスコーレに
ここで、なぜラ・クールが農村電化の手段として風車を選んだかについて考えると、そこには単なる技術・経済上の条件以上のものが存在することが明らかになる。当時、小型蒸気機関による発電はすでに実用段階に入っていた。しかし、蒸気機関にしろ石油エンジンにしろ、外部からの燃料供給によって動く動力源はすべて、肝心の燃料の供給を断たれるととたんに用をなさなくなる。しかも化石燃料は多くの場合、農民達の暮らすデンマークから遠く離れた異国の地で採掘され、様々な資本の支配する流通経路を経て漸く供給されるものである。農民自身がコントロールできる等身大の技術を求めたラ・クールが、現在のように無公害エネルギーとしての風車が注目されるずっと前から風車発電にこだわっていたのは、風車発電のエネルギー源である風が、石油のように中東 デンマーク風車の歴史は20世紀に入ってすぐ、途絶えてしまう。化石燃料による経済的な発電システムの普及の前には、ラ・クールの風車発電などひとたまりもなかった。デンマークのエネルギー政策は基本的に石油と原子力を中心にしたまま、1960年代を迎えることになる。しかしながら、風車は人々の心の中に、単なる過ぎ去った過去へのノスタルジーにはとどまらない、立派なエネルギー資源の一つとして存在し続け、デンマーク社会の通奏低音となっていたことはたしかだ。事実、第二次世界大戦中の物資不足の折りには、一部地域で発電用風車が復活することもあったのである。 デンマークにおいて、今日まで続く風車発電の第二次ルネッサンスのきっかけとなったのは、60年代に計画された原子力発電所建設への反対運動、それと70年代初頭のオイルショックという二つの事件である。オイルショックについて、デンマークではそれを近代の文明システムが根本から抱える問題ーつまりラ・クールが化石燃料エネルギーに見いだした問題点と本質的に全く同じものーと考え、その問題点の見直しと抜本的な改革へと舵が大きくきられたのである。反原発運動にしても、反対派が原発という巨大システムに見出した問題は、単なる地域エゴの域を超えてひとつの文明批判にまで達していた。単に原発に反対するだけでなく、そのオルタナティヴを同時に作り出すことまで併せて、一つの完結した運動であるというのが、その当時のデンマークの常識であった。 デンマークの有名な風車の一つに、通称ツヴィンドミルと呼ばれる2000kw級の巨大風車がある。ユトランド半島の西海岸に位置するツヴィンド・ホイスコーレの生徒達が、学校のエネルギーを自給するため、1970年代半ばに自力で作り上げた風車である。この風車の開発の歴史は、それだけで何冊もの本が書けるほどのドラマに満ちており、いわばデンマーク版プロジェクトXといった趣がある。ここでは彼らの成し遂げたことの革新性、そしてそこから垣間見えるデンマークの環境思想について、すこし説明しておきたい。 この風車について重要なのは、これが反原発運動の一環として作られたという事実である。当時、デンマークでは電力会社やリソー研究所(国立原子力研究所)において原発建設計画が本格化しつつあり、それに対し、国民の間では広汎な反対運動が広がりつつあった。そして、後にデンマークの自然エネルギー開発の中心となったフォルケセンターの創立者となるプレーベン・メゴアに代表されるような、「20kw×30000台の風車を全国に作れば60万kwの原発など要らない」をスローガンにした風車の普及活動がさかんに行われた。これまでにも述べてきたように、この運動は、オルタナティヴとしての風車やバイオマスの開発と不可分に結びついたものであった。ツヴィンド・ホイスコーレの巨大風車は、それだけで見るといかにも孤高の英雄的大事業のようにも思えるが、現実にはこのようなデンマーク全体、さらには世界中の意識ある人々を巻き込んだ大きな流れの一つの露頭であることがわかる。これは余談になるが、フォルケセンターの前身の組織は、ジョン・レノン(彼の最初の妻はデンマーク人である)やベトナム脱走兵など、国籍も職業も様々な人間が出入りする、一種の解放区、無縁の地であった。このような自由な空間から生まれたものが、 ジョン・レノンの名曲「イマジン」であり、デンマーク風車であるという事実は、非常に興味深く、さらには人類史普遍のダイナミズムを感じさせるものがある。 その後まもなく、デンマークの風車発電機産業は大きな転換点に差し掛かることになる。1978年にアメリカ大統領に就任したジミー・カーターは、自然エネルギーによって作られた電力を電力会社が買い取ることを義務付けたパーパー法を施行し、その結果、カリフォルニア州を中心として、1980年代初めに風車建設ブームが沸き起こった。その当時、世界で唯一まともな風車発電機産業があったのはデンマークであり、当然の如く怒濤の注文が殺到した。それまで鍛冶屋の家内工業程度の規模であったデンマーク風車業界は、これを契機に近代的な工場生産と株式会社組織を備えた一大産業へと変貌を遂げることとなり、現代に至っている。 今や完全に企業論理が支配するところとなった風車業界であるが、その出発点となった無縁の精神はしぶとく生きつづけている。ヴェスタスやノルデックス等の大企業が作るメガワット級風車にすっかり覆い尽くされてしまったデンマーク風車業界でも、一家に一台風力発電機という当初の理想を守り続け、銭にもならない個人用小型風力発電機の開発に尽力する人が少なからずいるのである。
近代科学に代表されるような、人間とその他のものを峻別し、全てを一元化して認識しようとするパラダイムは、確かに計り知れない物質的進歩を我々の生活にもたらしたといえるだろう。しかし、それは同時に、現生態系の存続を危うくさせる程の環境破壊と、自然から切り離されてしまった人間精神の貧困化という、現在の世界を覆い尽くす二つの巨大な不均衡を創り出すこととなった。ここで取り上げた風車業界の例は、さまざまなオルタナティヴ社会運動の中でも比較的早くに体制化/有縁化を果たした例である。しかし、それは既存の秩序の中に唯々諾々として組み込まれたわけではなく、むしろ秩序の方がそれにあわせるよう進化してきたため、結果的に組み込まれたように見えるというのが真実のように思う。現代社会の抱える数々の閉塞を打ち破り、未来へ希望を見出してゆくあたらしい思想を、われわれは皆、心の底から待望しているのだ。 このような広汎な人々の集合意識に支えられて、新たな形をまとった無縁の力が次々と社会の表面へと噴出し始めている。ありとあらゆるボーダーを越えて縦横無尽に活動するNGO・NPO、個人ならぬ“孤人”の集合体と化してしまった社会を生き返らせる新しい地域コミュニティー構築の試み、人知を超えた怪物となってしまった経済システムをもう一度人間の手に取り戻すための地域通貨、これまでの硬直化した産業構造を打ち崩す力を秘めた分散型のエネルギー/情報ネットワーク等々、従来の近代文明のパラダイムとは明らかに異質なものを持った動きの数々は、いずれもここ十数年の間に急速にわれわれにとって身近な存在になってきたものばかりである。そして、さらに重要なことに、これらの多くは社会から隔絶したアカデミックな知ではなく、デンマーク風車の例に見られるような、現場での絶え間ないスクラップアンドビルドの繰り返しの中から手づかみで獲得された、いわば野生の思考ならぬ野生の知/身体知とでもいうべきものを拠り所としてる。現代の無縁は思想と身体のシンクロする境界領域から発生したのである。 このように、アカデミズムの外で次々と革新的な試みが続けられている一方で、学問、とりわけ人文学はその危機が叫ばれるようになってもはや久しい。しかし、現在進行中の歴史的大転換の中で、自然と人間、生命と非生命、持てるものと持たざるものといった単純な二元論を打ち破り、人間原初の自由と対称性を回復してゆく上で、人文学がこれまで蓄積してきた方法論が大きな役割を果たし得る可能性は十二分にある。次世代の人文知を創造する、つまり本当の意味で“網野善彦を継ぐ”とき、デンマーク風車の事例が示すように、真にクリエイティヴな仕事は、学会と研究室だけで起きるものではないという事実が重要な意味を持ってくる。それは、ともすれば現実との接点を喪って学問のための学問に堕するか、もしくは権力や巨大資本のお先棒を担ぐかのどちらかの陥りがちであった日本の人文学の中に、真に有効な社会への回路を穿つことに他ならない。未来の人文学は人類史を貫く無縁という名の伏流水への飽くなき探求とともに、その流れ行く先までも見据えていかなければならないのである。極度に分断され、もはや全体としての生を生きる事が困難になった現代を根底からひっくり返し、それに代わる新たな価値規範を歴史的文脈からひとつひとつ見出してゆくことは、現代において人文学のなし得るもっとも有意義な仕事ではないかと思う。
|























